【MTG公式】記事情報:トークンの歴史、パート2




































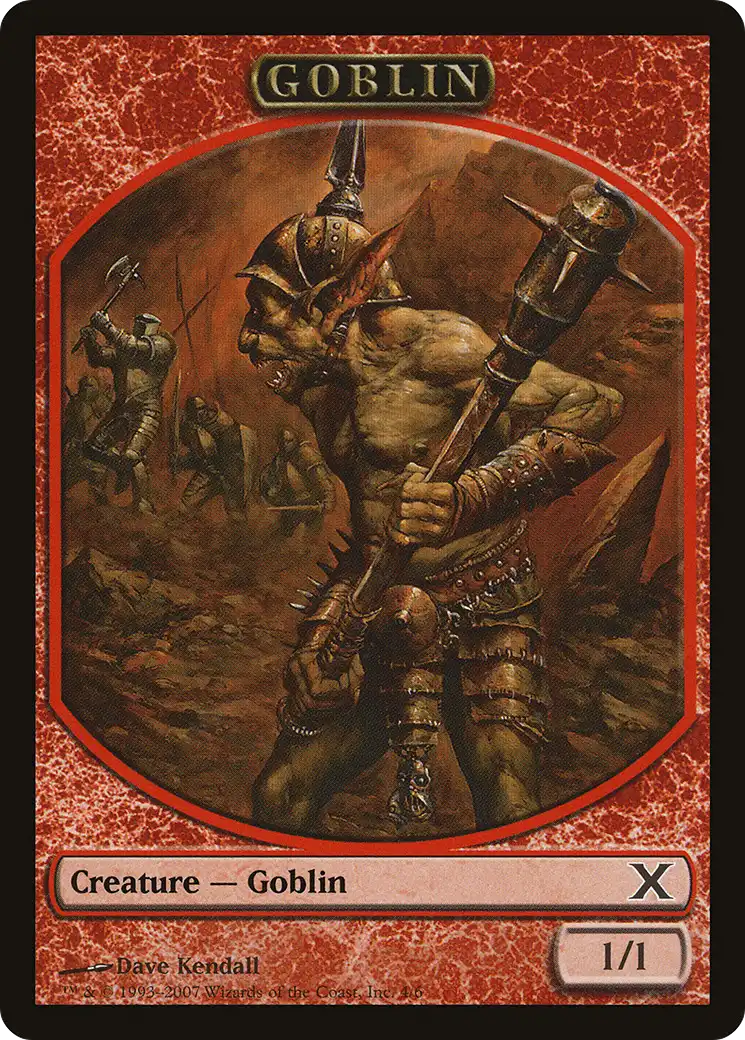

































マジック:ザ・ギャザリング(MTG)では、トークンが長年にわたりゲームデザインの一部として進化してきました。
2000年以降のセットでは、単なるクリーチャーの代用品にとどまらず、ゲームメカニズムの中核を担う存在へと成長しています。
本記事では、2000年代以降のトークンのデザイン史を振り返りながら、どのように役割が拡張されてきたのかを要点ごとに解説します。
要点解説
-
トークン拡張のはじまり(2000〜2003年)
「完全な反射」や「菌獣の横行」など、特定条件やメカニズムに応じたトークン生成が登場。
「秘宝の突然変異」「オーラの突然変異」では、相手のパーマネントを破壊して自軍にトークンを生成。 -
機能性の進化(2004〜2007年)
「鏡割りのキキジキ」によって一時的なコピー・トークンの概念が導入。
「倍増の季節」はトークン生成数を倍増し、トークン戦術を一変させた。
「黄昏の群れ操り」ではトークンの消失をトリガーとする能力が登場。 -
セット全体への構造的な組み込み(2008〜2011年)
『エルドラージ覚醒』でエルドラージ・落とし子がセット全体に登場。
0/1トークンがマナ加速の中核を担うなど、構造的メカニズムとしてトークンが機能。 -
非クリーチャートークンの登場と多機能性(2012年〜)
「金箔付け」「黄金の呪いのマカール王」によるアーティファクトトークンの導入。
「皇帝の仮面」は初のエンチャント・トークンを生み出した。
「居住」などでは、場のトークンを複製する新しい戦略が可能に。 -
プレインズウォーカーとトークンの共存
「黄金のたてがみのアジャニ」「野生語りのガラク」がトークンを生成し、自身を守るメカニズムとして採用されるようになる。 -
トークン人気と普及
「獣性の脅威」など、複数のトークンを同時に生成するカードも登場。
2007年以降はブースターパックにもトークンが印刷され、より広く一般化された。
まとめ
2000年代以降、トークンはMTGにおいて戦術的・構造的・物語的な役割を果たす重要な存在となりました。
「倍増の季節」や『エルドラージ覚醒』といったカードやセットの登場により、プレイヤーに新しい遊び方や構築の幅を提供しています。
さらに、プレインズウォーカーや非クリーチャートークンの採用により、トークンは単なる補助的存在ではなく、戦略の核となる存在へと進化しました。
今後もトークンは、マジックの進化を象徴する仕組みとして注目されることでしょう。
次回の記事では、非クリーチャートークンやさらなるメカニズムへの展開について紹介される予定です。
MTG公式様にて記事が公開されました。
MTG公式様の記事をチェック
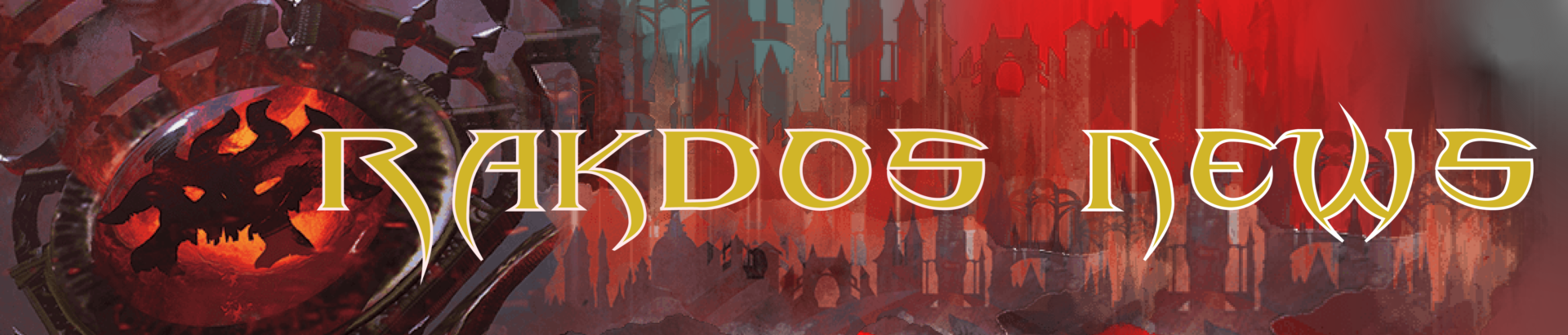




コメント