【MTG公式】記事情報:デザインファイル:『ウルザズ・デスティニー』、パート1
『ウルザズ・デスティニー』は1999年に発売されたマジック:ザ・ギャザリングのセットで、「ウルザ・ブロック」の最終弾として登場した。
本記事は、当時セットのリードデザイナーを務めたマーク・ローズウォーターによる開発舞台裏を紹介する「Design Files」シリーズの一部である。
セット制作時の試作カードや採用に至る過程、そして最終的に採用されなかったアイディアなど、貴重な記録が語られている。
●要点解説
-
開発体制と背景
-
ローズウォーターは当初デベロッパー(調整担当)として雇われたが、後にデザイナーに転向。
-
『テンペスト』に続き、『ウルザズ・デスティニー』がリードデザイン2作目。
-
当時はデザイナー不足で、彼一人でセット全体をデザイン。
-
-
主なメカニズムと構成
-
セット全体のメカニズムはエコーとサイクリング。
-
エコー:翌ターンに追加コストを支払わないとクリーチャーを失う仕組み。
死亡時効果と組み合わせることでカードの見返りを設計。 -
サイクリング:カードを捨てて新しいカードを引くメカニズム。
これを戦場のカードにも応用し、「戦場からのサイクリング」という非公式アイディアが誕生。
-
-
試作から製品化された代表カード例
-
「ゴブリンの司令官」:登場時と死亡時に1/1のトークンを生成するエコー持ちのカード。
当初は4体生成でダメージ効果付きだったが、強すぎたため修正。 -
「心の管理人」:マナ加速+サクリファイスでドローできる「戦場からのサイクリング」カード。
デザインから印刷まで一切変更なし。 -
「疫病犬」:死亡時に全クリーチャーに-1/-1を与える。
サクリファイスによるドロー機能付き。 -
「遺宝安置所の修道士」、「カワセミ」:死亡時トリガーを持つ典型的なクリーチャー。
-
「ヤヴィマヤの古老」:サクリファイスで基本土地2枚をサーチする能力へと変更され、強カードに昇格。
-
「夜のチャイム」:オーラが死亡トリガーを付与する新型除去、構想そのままに印刷。
-
-
独自の拡張アイデア
-
成長オーラ群(例:「弓術の訓練」, 「私的研究」など):各ターンで成長カウンターを置き、徐々に効果が強くなる仕組み。
-
予見者サイクル:手札にある同色のカード枚数を参照してスケーリング能力を持つウィザード・サイクル(例:「ジャスミンの予見者」, 「ベラドンナの予見者」)。
-
白の新要素「フリッカー」:対象を「戦場に再び登場させた」と扱い、登場時効果を再利用可能にするギミック。後に定番メカニズムに。
-
-
失敗ではなく進化したアイディア
-
元々『テンペスト』用に用意されたエコーやサイクリングは過剰要素と見なされて一度は削除されていた。
-
過去の試みが『ウルザズ・サーガ』以降で再登場し、のちのスタンダードセットやモダンデッキにも影響を与える。
-
-
ロボトミーの拡張系
-
以前の人気カード「ロボトミー」の影響で、各パーマネントタイプ(クリーチャー、エンチャント、アーティファクト、土地、インスタント/ソーサリー)に対応する「除去+デッキ追放」カードが各色に展開された。
-
例:「一掃」(白)、「撲滅」(黒)、「木っ端みじん」(緑)、「塩まき」(赤)、「鎮圧」(青)。
-
●まとめ
『ウルザズ・デスティニー』は、マジック史上の中でも開発陣の創造性と実験性が強く反映されたセットだった。
マーク・ローズウォーター一人でセット全体を構築したこの試みは、後のマジックに多大な影響を与えた要素をいくつも生み出した。
エコー、サイクリング、フリッカー、成長型オーラ、スケーリング能力持ちクリーチャーなど、いずれも今ではスタンダードな要素となっている。
興味深いのは、当時は一部しか認知されなかった「戦場からのサイクリング」や、「死亡時誘発のオーラ」といった仕組みが、現代のマジックでは一般的になりつつあるという点だ。
長年プレイしているファンなら、懐かしさと発見を兼ね備えた内容となっているだろう。
ちなみに、こうした開発秘話は現在も公式コラムなどで随時公開されており、カードデザインに興味がある人には貴重な資料である。
マジックの奥深さを再確認する機会として、ぜひ一度『ウルザズ・デスティニー』を振り返ってみてはいかがだろうか。
なお、当時のブースターパックは1パックあたり約420~560円で販売されていたが、現在では未開封ボックスがコレクター市場で数万円以上の価値を持つこともある。
次回のコラムでは、今回触れられなかった未採用カードや開発中止となったアイディアについても語られる予定だ。続報にも注目したい。
MTG公式様にて記事が公開されました。
MTG公式様の記事をチェック
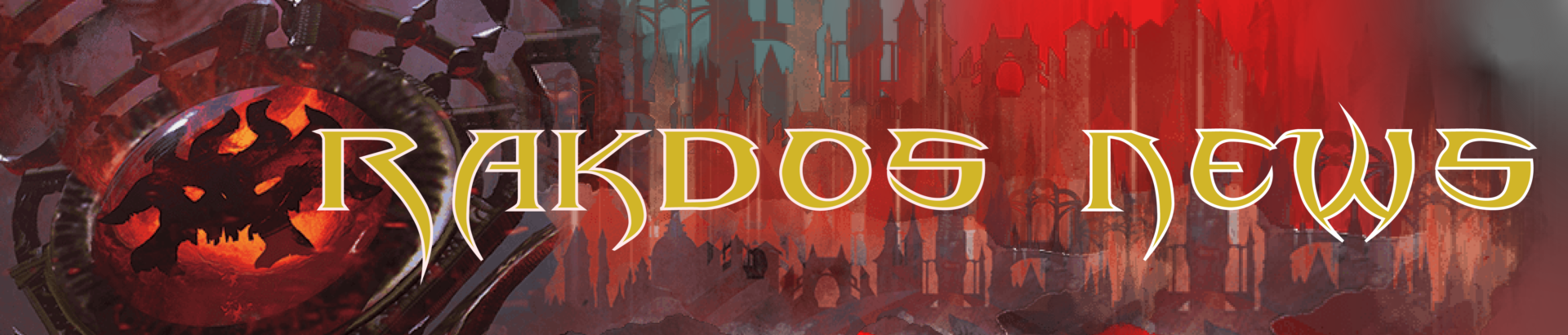



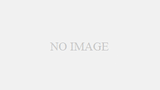
コメント