【MTG公式】記事情報:トークンの歴史、パート1








































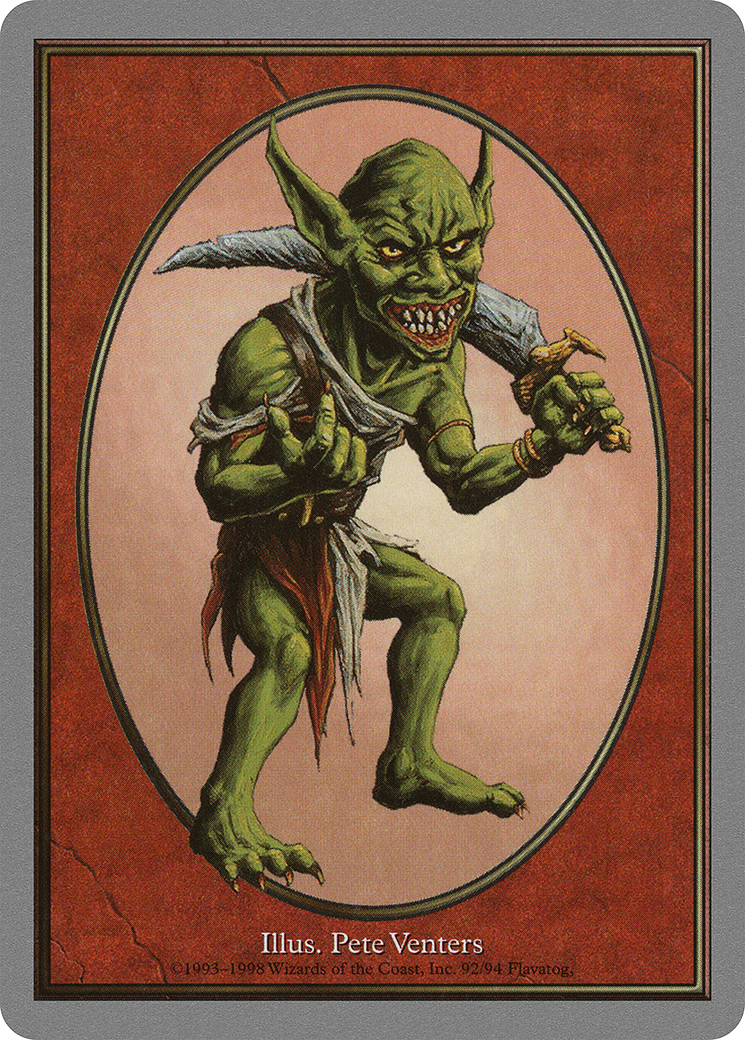








MTGでは、ゲーム内の多くの要素がカードを通じて表現されますが、それだけでは不十分な場合もあります。
そうしたときに用いられるのが「トークン」です。
トークンはデッキに含まれない永続物であり、さまざまなデザイン実験やゲーム体験の拡張に使われてきました。
本記事では、その歴史をたどりつつ、トークンの進化と設計上の革新についてご紹介します。
要点解説:トークンの歴史と進化を振り返る
1. アルファ期:トークンの始まり
-
初登場は「蜂の巣」カードで、「1/1 飛行アーティファクト・クリーチャー・トークンを生成」と指定。
-
初代トークンとして、タップ状態の区別方法や死亡時の扱い(墓地に行かず消える)も初めて明文化。
-
2. アラビアンナイト:変身と乱数の表現
-
「ルフ鳥の卵」:感受性のあるタマゴが孵化して4/4飛行クリーチャーになるトークン。
-
「スレイマンの壺」:成功で5/5飛行ジン、失敗で自分に5点ダメージというランダム性。
3. アンティキティー:トークンとカウンターの融合
-
「テトラバス」では +1/+1カウンターとトークンを相互変換可能なデザイン。
-
トークンに「エンチャントを付けられない」といった制限も初登場。
4. レジェンド:ルールと多様性の確立
-
トークンという用語の正式採用及び基本ルールへの組み込み。
-
多様な効果:
-
「Master of the Hunt」:バンド能力
-
「Boris Devilboon」:マルチカラー・トークン
-
「Hazezon Tamar」:生成トークンの存在が元のクリーチャーに依存
-
「毒蛇製造器」:毒カウンターを与える可能性を持つ毒蛇生成ギミック
-
5. ザ・ダーク / フォールン・エンパイア:機構重視のデザイン
-
「あまたの舞い」:カードのコピーとしてのトークン。
-
『フォールン・エンパイア』:色ごとにトークン生成手段を多様化し、「トークンの盤面」で戦う設計を明確化。
6. 以降のセット:用途拡大と演出強化
-
『アイスエイジ』:「カリブー放牧場」で初のオーラによるトークン生成。
-
『ホームランド』:除去でトークンが生成される「影写し」。
-
『アライアンス』:
-
「Errand of Duty」:インスタントとして初のトークン生成。
-
「バルデュヴィアの死者」:速攻付きトークンを生成し、ダメージソース化。
-
「Splintering Wind」:累積起動型で自爆トークン生成。
-
「饗宴か飢餓か」:除去と生むクリーチャーの二面性。
-
-
『ミラージュ』:
-
「死後の生命」:除去されたクリーチャーの代わりにトークンを生成。
-
「高波」:一時的な防御トークン。
-
「屍肉」:撃破したクリーチャーのサイズに応じ複数トークンを生成。
-
-
『ビジョンズ』:「大イモムシ」:マナでトークン→変身メカニズムに。
-
『ウェザーライト』:「うろの下僕」:マナを使った任意トークン生成。
-
『テンペスト』:
-
「魂のフィールド」:死亡したクリーチャーのトークン生成。
-
「霊の鏡」:エンチャントでトークンを生成し、自身を犠牲に破壊可能。
-
「肉占い」:1マナで2/2のゾンビ・トークンを生成しつつ墓地を利用するデザイン。
-
-
『ストロングホールド』:
-
「モグの横行」:相手クリーチャーをより小さい数のトークンに変える+自分も犠牲にする粛々としたデザイン。
-
「ヴォルラスの研究室」:トークンの色とタイプを自由選択可能に。
-
-
『Unglued』:トークンそのものをカード化するユーモア溢れる実験。
-
『ウルザズ・サーガ』〜『ネメシス』:各種トークン生成の深化、ミラーマッチやトーナメント戦略にも使われる。
まとめ:トークンはMTGの進化を象徴する設計ツール
MTGにおけるトークンは、単なる補助的要素に留まらず、「新たなギミックや戦略、演出を生み出す柔軟性の源泉」として設計の中核を担ってきました。
初代の曖昧な表現から、明確なルール化・バリエーション化を経て、「変身」「代替」「ランダム」「拡張表現」「リソース回収」など多様な役割を担うようになりました。
トークンの歴史を追うことで、MTGデザインにおける創造性の進化と、カードゲームが単なるカードの集合以上に広がった背景を垣間見ることができます。
次回は21世紀以降のトークンデザインを追っていきますので、どうぞお楽しみに。
MTG公式様にて記事が公開されました。
MTG公式様の記事をチェック
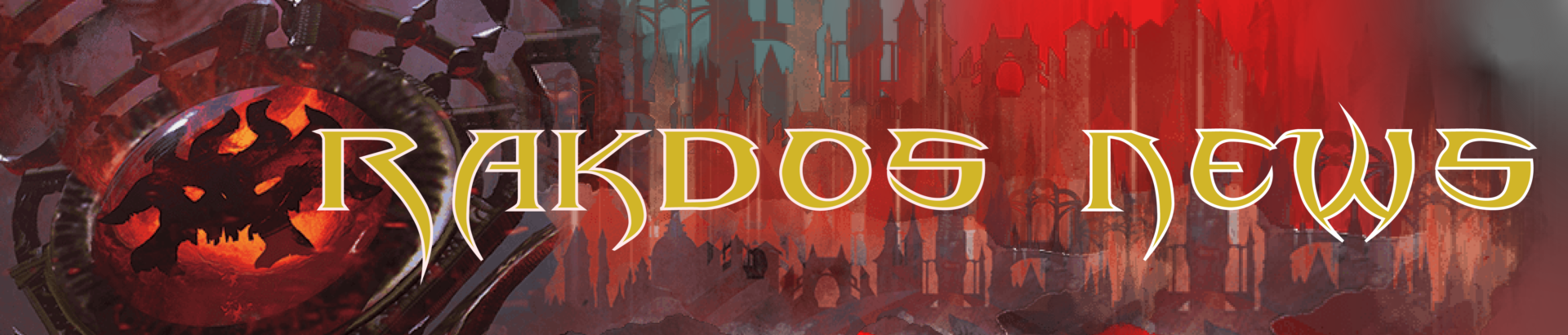




コメント