【MTG公式】記事情報:Nuts & Bolts #17: 自分に合ったメカニズムを見つける、パート2。




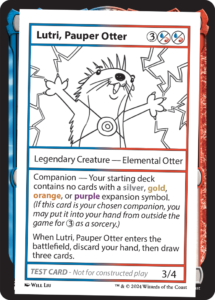
マジック:ザ・ギャザリングのカードデザインの裏側を解説する恒例の「Nuts & Bolts」シリーズ。
今回はメカニズム(カード固有の仕組みや能力)をどのように「仕上げていくか」に焦点を当て、デザインからプレイテストまでの具体的なプロセスを丁寧に解説しています。
自作メカニズムを持つデザイナーやカジュアルプレイヤーにも非常に役立つ内容です。
要点まとめ
-
メカニズムの肉付けは試行錯誤の繰り返し
-
まずは既存セットのコモンカードを参考に、自作メカニズムを使って似たカードを多数設計。
-
色やカードタイプに合わない場合でも、それ自体がメカニズム理解の一助となる。
-
-
マナコストは類似メカニズムを参考に
-
例えばコスト軽減系なら召集、選択効果ならキッカー、回避能力なら潜伏と比較。
-
既存の同タイプ・同サイズのクリーチャーを調べて基準を設定。
-
バランスが取れていなければプレイ中に調整しても問題なし。
-
-
初期プレイテストの方法
-
40枚デッキを組み、自作メカニズム入りカードは4〜8枚を目安に。
-
残りのカードは既存カードで構成し、変数をコントロール。
-
手札事故が起きたら引き直し可、マリガンの必要なし。
-
-
プレイテスト後の振り返り質問例
-
楽しかったか?
-
どのカードがうまく機能し、どれが機能しなかったか?
-
メカニズムが活躍するのはどの状況・カードか?
-
理解されやすかったか?他のプレイヤーの反応は?
-
-
「アズファン(as-fan)」で頻度を数値化
-
「1パックに平均何枚そのメカニズムのカードが入るか」を数値化。
-
例:コモンで7枚、アンコモン7枚、レア3枚含む場合、アズファンは約1.25。
-
バランス調整の参考になり、セット全体への影響度を数値で把握できる。
-
-
改善のための心構え
-
テストとフィードバックの反復が最重要。
-
思い切った実験を恐れない。
-
「自分の赤ちゃん(メカニズム)を醜いと言える勇気」を持つ。
-
他メカニズムやシナジーとの関係にも注目する。
-
カードは新メカニズム中心に構成し、説明過多にしない。
-
-
完成の見極め方
-
3回連続で大きな変更が出なくなれば、ほぼ完成と見なせる。
-
完璧を目指しすぎず、期限(締切)を設けて仕上げることが大事。
-
まとめ
メカニズムの設計から完成までは、ひたすら「試して、直す」の繰り返しです。
今回の記事では、プレイテストを通してどのように楽しさや問題点を見つけ、洗練させていくかが具体的に示されていました。
特にアズファンの概念や、テスト中にコストや効果を柔軟に調整する姿勢など、プロの開発現場ならではの知見が満載です。
自作カードやセットを作っている人にとって、今回の内容はまさに必読。自分のメカニズムがどこで輝くか、どのようにプレイヤーに受け取られるかを見極める手助けになるでしょう。
次回のデザインファイル記事も、引き続き注目です。
MTG公式様にて記事が公開されました。
MTG公式様の記事をチェック
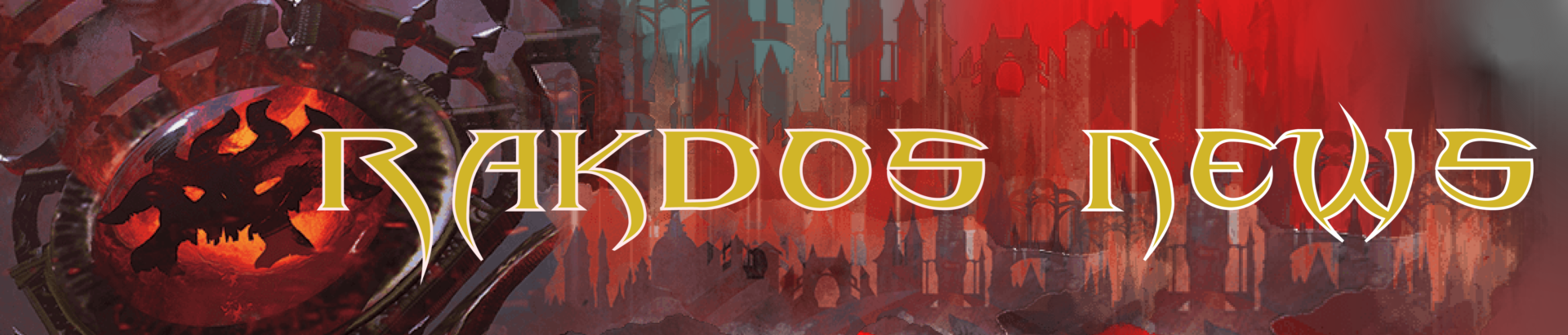




コメント