【MTGRocks】記事情報:クラシックなMTGスタンダードのアーキタイプが機体を大幅にアップグレード





MTGの最新セット『霊気走破』がスタンダード環境に登場し、早くも多くのデッキに大きな影響を与えている。
特に「機体」カードが各種アーキタイプに採用され、強力な動きを見せている。
本記事では、環境に適応しつつある注目の機体カードを紹介し、それぞれのデッキにおける役割を解説する。
要点解説
1. 「ガスタルの激ヤバ車」(赤単アグロ)
- 4/2の速攻持ちで、高い攻撃力を誇る。
- 「切り崩し」や「喉首狙い」といった除去呪文を回避可能。
- 倒されても後から復活できるため、継続的にダメージを与えられる。
- 防御性能が低く、赤単ミラーでは「噴出の稲妻」や「塔の点火」に弱い。
- 「太陽降下」などの全体除去を回避できるため、ミッドレンジやトークンデッキへの対策として有効。
- 「ウラブラスクの溶鉱炉」と似た役割を持つが、より即効性がある。
2. 「ボヤージャーの滑空車」(ボロス・召集)
- 軽量で「上機嫌の解体」との相性が抜群。
- 「上機嫌の解体」が生み出す3体のトークンをすぐに搭乗させられる。
- 必要に応じて、「上機嫌の解体」の生け贄対象としても機能。
- 「遠眼鏡のセイレーン」を採用する青タッチのジェスカイ・召集より、2色の安定したマナベースが選択可能。
- 「入れ子ボット」と併用する形で実験的に採用されている。
3. 「轟音の速百足」(グルール・昂揚)
- 5/5のトランプル持ちで盤面制圧力が高い。
- 「野火の木人」などのカードと組み合わせて、大型クリーチャーを強化可能。
- 「継ぎ接ぎのけだもの」などの軽量クリーチャーで容易に搭乗可能。
- アーティファクトが多いデッキではデリリウムを容易に達成できる。
- セレズニア・トークンデッキとも相性が良く、「収集家の檻」型のデッキにも採用の余地あり。
4. 「重厚な世界踏破車」(ドメイン・ランプ)
- 「山積みの収穫」よりも直接的なランプカードではないが、長期戦で優れた働きをする。
- 「ミストムーアの大主」のトークンだけで搭乗可能。
- 攻撃時に土地をサーチし、次第にサイズが強化される。
- 「ホーントウッドの大主」と役割が似ているため、大量採用はされにくいが、デッキの冗長性を確保できる点で評価される。
- プレインズウォーカー(特に「悪夢滅ぼし、魁渡」)への対応策としても有効。
5.「 屑転がし」(ゴルガリ・ミッドレンジ)
- 6/6のトランプル持ちで、序盤からライフを吸収する能力を持つ。
- 搭乗コストが低く、使い勝手が良い。
- 「黙示録、シェオルドレッド」のような強力な競争相手がいるものの、デッキに適した構築なら十分採用価値がある。
- 「恐血鬼」などの自己再生能力を持つクリーチャーと組み合わせると、安定した搭乗が可能。
- 「苔森の戦慄騎士」を採用する伝統的なゴルガリ・ミッドレンジデッキにもフィット。
まとめ
1. 『霊気走破』の影響で「機体」カードが急速に環境に適応
- これまで構築で使われにくかった機体カードが、多くのデッキに採用され始めた。
- 「赤単アグロ」「ボロス・召集」「グルール・昂揚」「版図・ランプ」「ゴルガリ・ミッドレンジ」など、多様なアーキタイプで活躍。
2. 環境適応のカギは「搭乗コストの軽減」と「戦場支配力」
- 軽量で簡単に搭乗できる「ボヤージャーの滑空車」や「ガスタルの激ヤバ車」は、テンポを重視するデッキに最適。
- 「轟音の速百足」や「重厚な世界踏破車」は、盤面をコントロールしつつ強力な攻撃を仕掛けるデッキ向け。
- 「Debris Beetle」のように、除去耐性や戦場での影響力が高いカードも注目されている。
3. 機体カードは今後も環境に適応し続ける可能性
- 『霊気走破』の登場直後にも関わらず、多くのデッキが機体を採用し始めている。
- 今後のメタの変化次第で、さらに多くの機体が採用される可能性がある。
『霊気走破』によるスタンダードの変化はまだ始まったばかりだが、機体の活躍には今後も注目していきたい。
MTGRocks様にて記事が公開されました。
MTGRocks様の記事をチェック
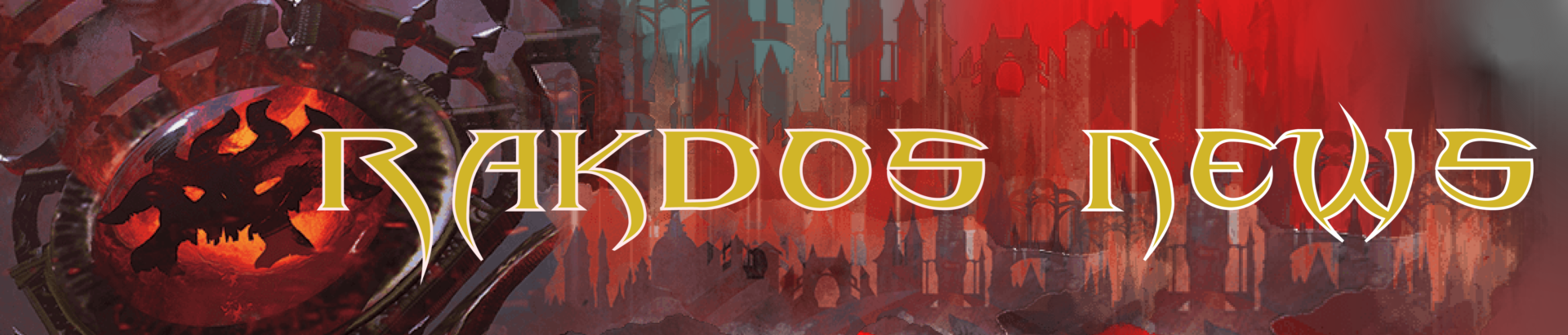




コメント