【MTG公式】記事情報:部族シナジーの歴史:パート3










過去2週間にわたり、カード名物の「タイプ(種族)を参照するデザイン」の歴史を振り返ってきました。
本日はその最終章。
各年で最も影響力のあった「典型的なタイプ・デザイン」をセレクトし紹介します。
要点解説
2013年:波使い
-
『テーロス』から登場。
エレメンタルのトークン生成を、自分のバフで調整するデザイン。 -
トークンの維持に自身の存在を必要とし、エレメンタル型デッキに自然と誘導される構成。
-
「残酷なハイソニア」のデザインでは、ゴルゴン型以外を一掃する「逆タイプ」効果が登場。
特定種族との相性構築を促進。
2014年:刃の隊長
-
『タルキール覇王譚』の戦士タイプを活用したドラフトアーキタイプの一体化。
-
敵対色の克服と型テーマに寄与する好例。
2015年:揺るぎないサルカン
-
ドラゴン型テーマの強化と、ブロック構成上の世界観演出。
デザイン上の時間旅行ストーリーとの整合性も秀逸。
2016年:戦墓の巨人
-
ゾンビ型を墓地と場に跨って強化するデザイン。
全ゾーンでタイプを参照する手法に成功。
2017年:太陽の化身、ギシャス
-
『イクサラン』より、恐竜族を主役とする設計。
アイコニックながらドラフトの自由度を削いでしまった反省例。
2018年:若葉のドライアド
-
苗木型の「昇殿」アップグレードデザイン。
トークン生成→強化と序盤から終盤まで一貫性あり。
2019年:限りないもの、モロフォン
-
『モダンホライゾン』より、どのタイプにも対応可能な万能リーダー。
全タイプに+1/+1とコスト軽減を提供し、エターナル層にも影響。
2020年:海門の擁護者、リンヴァーラ
-
『ゼンディカーの夜明け』より、RPGパーティ4種族構成(クレリック、ならず者、戦士、ウィザード)を強調。
複数種族によるスケール型の型設計。
2021年:ティアマト
-
『フォーゴトン・レルム探訪』とのコラボ。
5色のドラゴンタイプで、ドラゴン・チューターとしての効果を搭載。
2022年:希望の源、ジアーダ
-
『ニューカペナの街角』から天使族向けリーダー。
大型クリーチャー型でも使いやすいタイプ誘導とコスト軽減。
2023年:うろつく玉座
-
『イクサラン:失われし洞窟』から、多種族を選んでコピー型効果を得られる便利カード。
型枠の柔軟性を高める設計。
2024年:渓間の洪水呼び
-
『ブルームバロウ』で展開された2色ペア動物型テーマの中から、様々な動物種族を対象にバフを与えるサイクルカード。構築誘導の新手法。
まとめ
-
様々な年を通じたType参照デザインの進化を概観しました。
-
「トークン生成+強化」「特定種族のバッジ効果」「多タイプ対応型リーダー」など多彩な表現が発展。
-
ひとつのタイプに偏らず、複数タイプを活かす設計や、構築やドラフトの強制感を減らす手法が進化。
-
今後も「部族メカニズム」は、柔軟な構築とテーマ性の両立を目指して進化し続けるでしょう。
MTG公式様にて記事が公開されました。
MTG公式様の記事をチェック
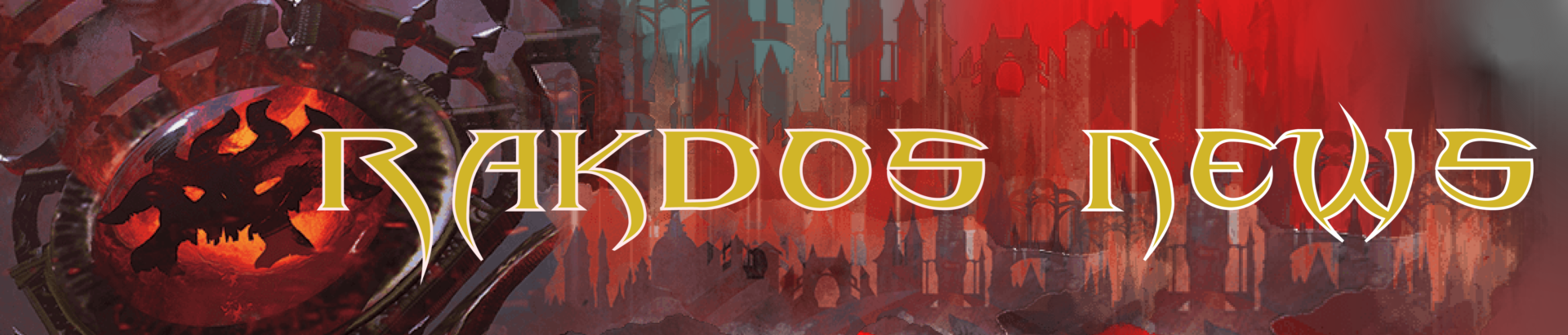




コメント