【MTGRocks】記事情報:MTG 革新的なセレズニアデッキがスタンダードでコントロールを取り戻す可能性あり。



長らくアグロとミッドレンジが支配するMTGスタンダードにおいて、コントロールデッキは苦戦を強いられてきました。
しかし、先週末に開催された320人規模のRCQで、セレズニア・コントロールが準優勝を果たし、コントロール復活の兆しが見え始めています。
本記事では、このデッキの特徴と今後の展望を解説します。
要点解説
1. セレズニア・コントロールの基本構成
-
トークン生成とカードドローの融合
- 「世話人の才能」でトークン生成と追加ドローを実現。
- 「人参ケーキ」がライフ回復、ドロー補助、盤面維持に貢献。
- 「跳ねる春、ベーザ」で序盤の劣勢を挽回し、トークンを増やす。
-
ドメイン戦略の採用
- 「豆の木をのぼれ」を軸に、「ホーントウッドの大主」や「ミストムーアの大主」と連携して大量ドローを実現。
- トークン生成と大きなクリーチャーによる後半戦のフィニッシュ力。
-
除去と盤面制圧
- 単体除去:「失せろ」、「眠りからの襲撃」。
- 全体除去:「別行動」、「太陽降下」。
- 「領事の権限」がアグロ戦略を抑制。
2. 現在のスタンダード環境における成果
-
RCQでの好成績
- グルール・アグロやゴルガリ・ミッドレンジといった主流デッキに2-0の成績。
- セレズニア・トークンやディミール・エンチャントには苦戦する場面も。
-
独自性のあるプレイスタイル
- 従来の青ベースコントロールと異なり、プロアクティブなミッドレンジ的アプローチを採用。
- アグロデッキに対しては「跳ねる春、ベーザ」の耐久力が効果的。
3. 今後の期待と課題
-
スタンダードにおけるコントロール復権の兆し
- RCQでの成功はコントロールデッキの可能性を示す重要な事例。
- しかし、現在の環境ではリアクティブな除去カードのパワー不足が課題。
-
ミッドレンジ化の懸念
- コントロールがミッドレンジ寄りの戦略を採用することで、アーキタイプ間の境界が曖昧になりつつある。
まとめ
セレズニア・コントロールの準優勝は、コントロールデッキに新たな方向性を示すものでした。
トークン生成とドメイン戦略を組み合わせた独自のプレイスタイルは、現環境において十分な競争力を持つことが証明されています。
ただし、リアクティブなカードの不足やメタゲーム全体のミッドレンジ化といった課題も浮き彫りになっています。
今後の環境変化次第では、こうした新しいコントロールの形がさらなる成功を収める可能性があります。
これからのスタンダード環境で、セレズニア・コントロールがどのように進化するかに注目です。
MTGRocks様にて記事が公開されました。
MTGRocks様の記事をチェック
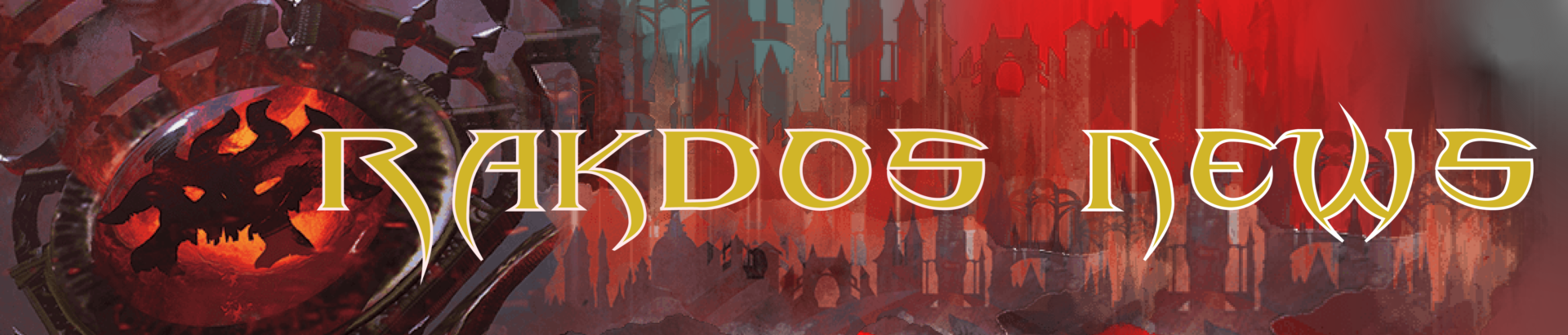




コメント