【MTGRocks】記事情報:13年前のMTGカードがスタンダードでまだ通用することを証明。



「漁る軟泥」は、時代を超えてスタンダードで活躍するカードの一例です。2011年に初登場し、現在もその汎用性とパワーで多くのデッキに採用されています。
本記事では、その魅力と現環境での役割を解説します。
要点解説
1. 「漁る軟泥」の基本情報
- カード性能:
- マナコスト:1G
- 能力:墓地からカードを追放(クリーチャーカードなら+1/+1カウンターを得て1ライフ回復)。
- 特徴:簡潔かつ効果的な墓地対策カードであり、成長するフィニッシャーとしても機能。
2. 「漁る軟泥」が評価される理由
- 柔軟性:
- 墓地対策として使えるだけでなく、ライフ回復と自身の成長も可能。
- 特にリアニメイトデッキや墓地を活用するコンボデッキに対して効果的。
- 速度と汎用性:
- 緑マナが許す限り、即座に複数回使用可能。
- 他の墓地対策カード(例:「虚空の力線」)よりも幅広いシーンで役立つ。
3. スタンダード環境での活躍
- 採用デッキ:
- ゴルガリミッドレンジ: メインボードに1~2枚採用され、長期戦でのアドバンテージ確保に貢献。
- コンボデッキ(例:テムール・洪水呼びコンボ):
- ライフ回復によるアグロ対策。
- 墓地対策が重要な環境での追加の防御手段として活躍。
- その他: ゴルガリ土地コンボや4色カウルドロンコンボでも採用例あり。
4. 競争相手との比較
-
主要な競合カード:
- 「虚空の力線」: 墓地全体を追放可能だが単発でコストが高い。
- 「ゴーストバキューム」: インスタントスピードの墓地対策に加え、長期戦での勝利手段を提供。
- 「静かな尾根の背中割り」: 墓地対策のほか、アーティファクトやエンチャントも除去可能。
-
差別化ポイント:
- 「漁る軟泥」は、墓地対策に加えて攻撃的な役割やライフ回復も可能。
- 単体で多機能なカードとして幅広いデッキで活躍。
まとめ
「漁る軟泥」は、そのシンプルで効果的なデザインにより、2011年の初登場以来、現代のスタンダード環境でも競争力を維持しています。
墓地対策に特化しながら、成長するフィニッシャーやライフ回復手段としても機能する点が評価されています。
スタンダード環境の多様な墓地活用戦略に対応するため、多くのデッキで採用されており、その使用率は新カードを凌駕するほどです。
「漁る軟泥」の活躍は、MTGのカードデザインが時を超えてプレイヤーに影響を与える例として、多くのファンに希望を与えています。
次回のデッキ構築では、このスリムで頼りになる軟泥を試してみてはいかがでしょうか?
「漁る軟泥」は『ファウンデーションズ』に収録されています。
『ファウンデーションズ』は↓から購入できます。
MTGRocks様にて記事が公開されました。
MTGRocks様の記事をチェック
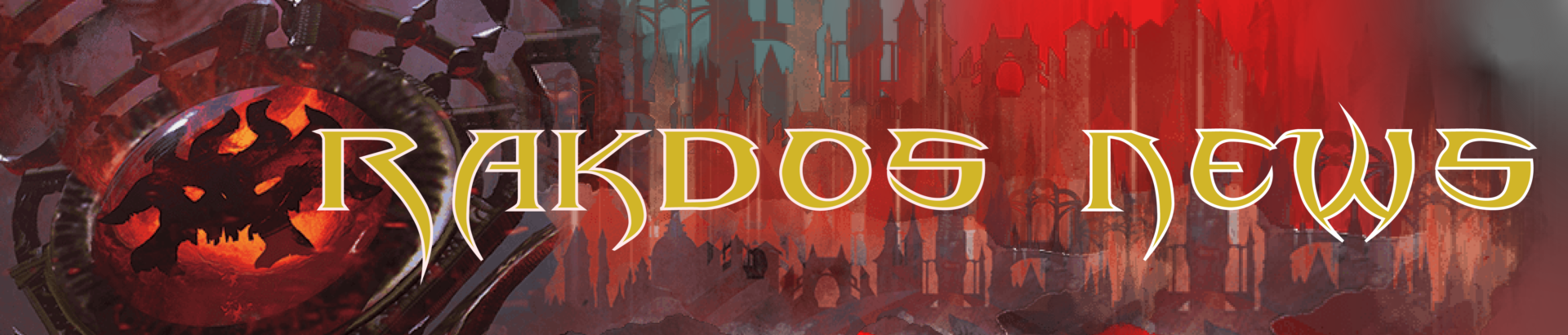


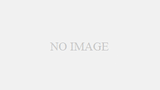

コメント