【MTGRocks】記事情報:議論を呼ぶMTGメカニズム、その未来をデザイナーが解説。



『マジック:ザ・ギャザリング』には、プレイヤーの間で議論を呼ぶメカニズムがいくつも存在してきました。
その代表格のひとつが「共闘」能力です。
当初は統率者戦に個性豊かな組み合わせをもたらす狙いでしたが、cEDHでの強さが突出し、デュエルコマンダーでは制限されるほどでした。
そんな「共闘」が新しい形で登場し、今後の方向性についてもマーク・ローズウォーターが説明しました。
要点解説
-
「共闘」の新形態登場
-
プレイステーションIPとのコラボ『ゴッド・オブ・ウォー』では、クレイトスとアトレウスが「Father & Son」という専用の共闘グループで登場。
-
従来の「との共闘」と異なり、カード名を直接指定するのではなく、グループ名で共闘が定義される。
-
-
「との共闘」との違い
-
「との共闘」なら統率者ゾーンでペアを組むだけでなく、片方を引いたときにもう一方をサーチ可能。
-
新形態ではサーチ機能がなく、99枚の中で引いた場合は相方を探せないため弱体化。
-
特に2枚だけの限定的なグループでは、旧方式より使い勝手が悪い側面がある。
-
-
利点と狙い
-
グループ化により、将来的に同じカテゴリー(例:「Survivor Partner」など)に複数のカードを追加できる柔軟性が生まれる。
-
既に『ストレンジャー・シングス』の「永遠の友」や『ドクター・フー』の「ドクターのコンパニオン」で試されていた方式。
-
こうした仕組みにより、既存の共闘(特にcEDHで強力なコンビ)をさらに強化する危険性を避けつつ、新しい風味を加えることができる。
-
-
プレイヤーからの懸念点
-
2枚限定の共闘にこの方式を使うと、「との共闘」の方が機能的に優れているケースがある。
-
例:アトレウスを単体で引いた場合、クレイトスを探せないため能力が弱体化してしまう。
-
「Father & Son」という狭いカテゴリ名は、後から新規カードを加えるのも難しい可能性がある。
-
-
旧方式も存続の可能性
-
『ファイナルファンタジー』コラボのアリゼー&アルフィノのように、99枚用の設計として「との共闘」が採用される事例もある。
-
よって完全に廃止されるわけではなく、用途に応じて使い分けられる模様。
-
まとめ
「共闘」はその強さゆえに議論を呼び続けてきましたが、新しい「グループ型共闘」によってフレーバー性と柔軟性を兼ね備えた形で再登場しました。
一方で、2枚限定のペアには旧方式の方が適している場面もあるため、必ずしも万能ではありません。
それでも、この新方式は「既存の共闘をさらに壊さずに、新しい物語的な組み合わせを作れる」という点で、今後の『ユニバース・ビヨンド』展開を支える重要な仕組みになるでしょう。
MTGRocks様にて記事が公開されました。
MTGRocks様の記事をチェック
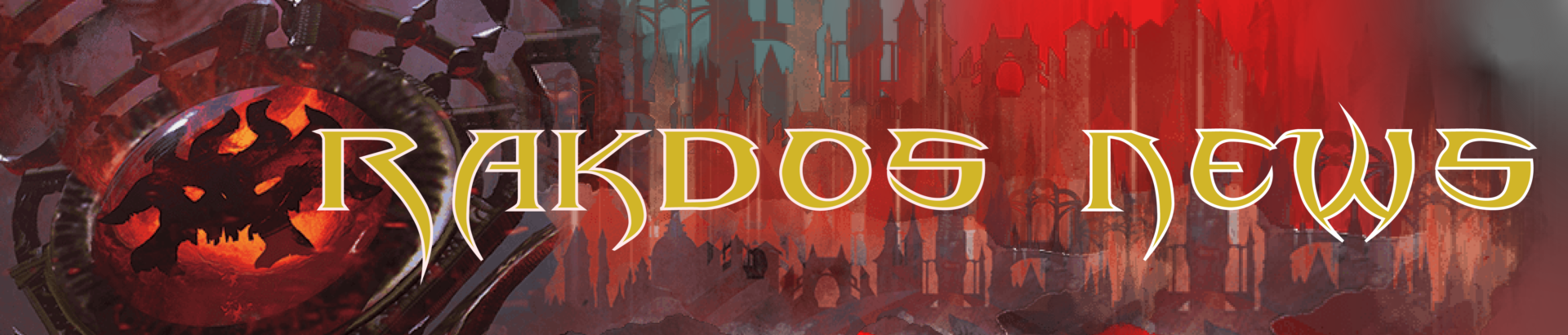




コメント