【MTG公式】記事情報:部族カードの歴史:第2回
マジック:ザ・ギャザリング(MTG)の「部族カード」は、特定のクリーチャー・タイプに関連するカード群であり、プレイヤーのデッキ構築やプレイスタイルに大きな影響を与えてきました。
本記事では、2003年から2012年までの年ごとに代表的な部族カードを紹介しながら、MTGにおける部族デザインの進化と革新について振り返ります。
要点解説
-
2003年:「墓生まれの詩神」
-
初めて「人間」タイプが導入され、クラスと種族の二重タイプが開始。
-
自身がゾンビであり、他にゾンビがいなくても最低1ドローできる設計で、部族カードの柔軟性を示す。
-
-
2004年:「飢えたるもの、卑堕硫」
-
「転生」という霊魂クリーチャー限定の部族メカニズムが登場。
-
「スピリットクラフト」と呼ばれる非公式メカニズムも登場し、部族とメカニズムの融合が進展。
-
-
2005年:「大蛇の守護神」
-
「献身」メカニズムが導入され、部族ごとに異なる効果を持つユニークな能力が誕生。
-
-
2006年:「宝革スリヴァー」
-
スリヴァー部族が復活。「能力付与型部族カード」が定着。
-
「群がりの庭」により複数のタイプを一括管理する「バッチ」概念の萌芽。
-
-
2007年:「鏡の精体」
-
ローウィン・ブロックで部族テーマを最大化。
-
「多相」メカニズムが部族間の架け橋に。
-
-
2008年:「刈り取りの王」
-
カカシという新部族を創出。
すべてのカカシがパーマネントを破壊する強烈な能力持ち。 -
単色混成マナの導入と大胆な部族効果の融合。
-
-
2009年:「海門の伝承師」
-
新部族「同盟者」が登場し、部族がセットの中心テーマに。
-
『基本セット2010』の「吸血鬼の夜侯」のような共感を呼ぶ部族デザインも増加。
-
-
2010年:「ウギンの目」
-
エルドラージ部族の前兆となるカード。部族に物語的・先取り的役割を付与。
-
「ウーラの寺院の探索」による「クラーケン・リヴァイアサン・タコ・海蛇」のバッチ概念が明確化。
-
-
2011年:「終わり無き死者の列」
-
イニストラード・ブロックで「軽度な部族セット」アプローチ。
-
部族カードを「選択型」にし、プレイヤーの自由度を拡張。
-
-
2012年:「魂の洞窟」
-
「部族フレンドリー」な土地として設計。
対打ち消し呪文用の実戦向けカードとして人気。 -
『アヴァシンの帰還』で天使部族を強化、M13で新しい「ロード」カード群も登場。
-
まとめ
部族カードの歴史は、単なる部族デッキの枠を超えて、ゲームデザインやプレイヤー体験における重要な進化を反映しています。
2003年から2012年の間に、部族はテーマ的・メカニズム的に深く結びつくようになり、プレイヤーの構築自由度を高めるとともに、セットの個性を際立たせる要素として発展してきました。
今後も部族カードは、新しい部族やメカニズムとともにマジックに新鮮な息吹を与え続けることでしょう。
MTG公式様にて記事が公開されました。
MTG公式様の記事をチェック
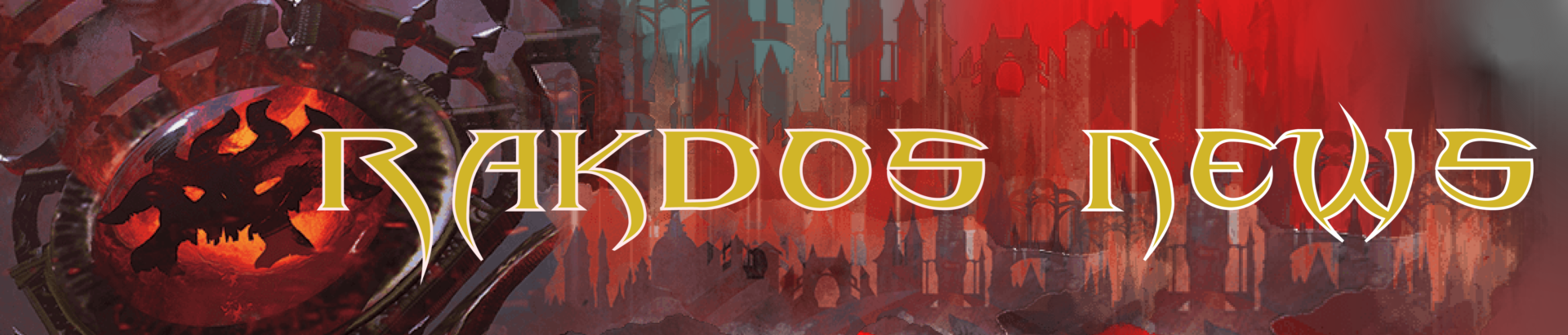




コメント